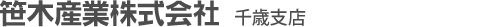北海道の住宅の歴史
北海道の住宅の歴史は、昭和28年に施行された「北海道防寒住宅建設等促進法」によって、大きく動き出しました。
寒冷地での住宅づくりに大きな影響を与えたこの法律により、昭和30年代から50年代にかけて、大量供給された
ブロック三角住宅が登場しました。

また、木造住宅でも暖かさを確保するための断熱材の使用が広がり、
長尺屋根を用いた複雑な屋根形状の住宅が増えていきました。
こうして北海道独自の形態や性能を持つ住宅の発展が始まったのです。

個人的には、この三角住宅が並ぶ光景がとても好きです。
この時期のさまざまな表情を持つ住宅にも魅力を感じます。私自身、昭和51年生まれですが、
子どもの頃から身近にあったのは、ブロック三角の家や屋根形状の複雑な住宅ばかりで、
遊びに行っていた友人宅もそんな家が多かったのを覚えています。この仕事で中古や既存住宅を扱うとき、
この年代の家に触れるたび、心が躍ります。
歴史ある外観やフォルムをできるだけ残しつつリノベーションを進めたいと、自然に思ってしまうのです。
その後、昭和50年以降は、低燃費で暖かい住宅を目指す動きが加速しました。
断熱性能の高い省エネルギー住宅の普及が進み、耐久性の向上、気密化、計画換気の導入など、
住宅性能は著しく進化しました。そして現在では、高性能・高気密・高断熱の住宅が主流となっています。
こうした背景を踏まえ、築年数の経った既存住宅や中古住宅の性能をどこまで向上させられるのか
——そのお話は、次回につづきます。