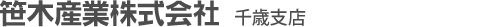【外壁工事 完工のご報告】
以前から進捗をご紹介していた外壁工事が、無事に完工しました。
Before

After

先日、足場が外れ、ついに建物の全体像がお目見え。
足場が外れた姿を見て、お客様と一緒に完成を喜べたことが印象的でした。
足場解体前には、窓の美装工事を行い、
その後、現場周辺のゴミ回収までしっかり対応して工事完了となりました。
お引き渡しの際には
「この外壁材を選んで正解だった」とお客様にも大変喜んでいただき、その言葉を聞けて、担当としてうれしかったです。
近隣の皆さまへのご挨拶回りも無事に終え、あとは雪解けを待って、改めてお家まわりの最終チェックとゴミ拾いを行う予定です。
工事期間中、ご協力いただいたお施主様、近隣の皆さま、本当にありがとうございました。